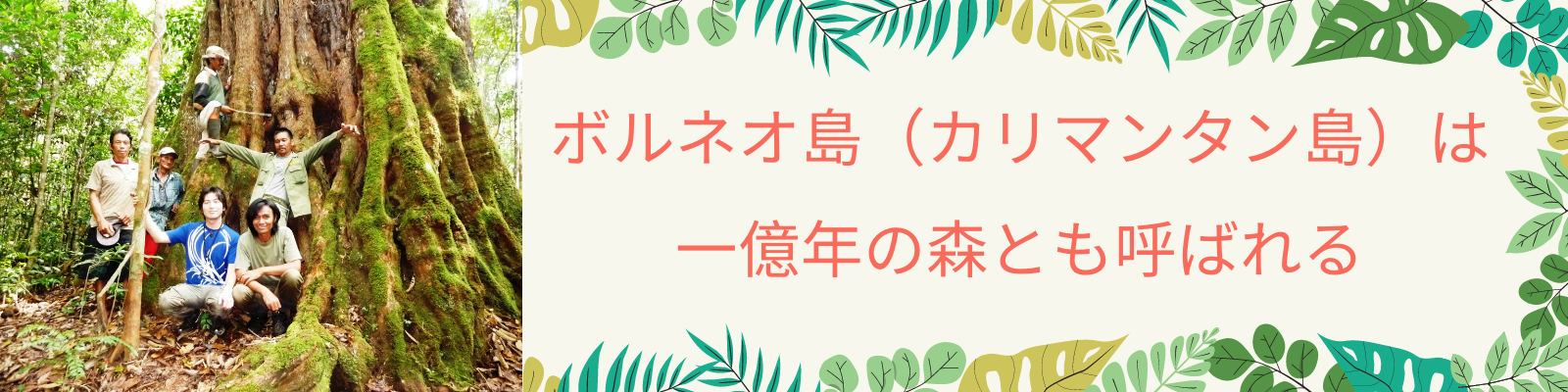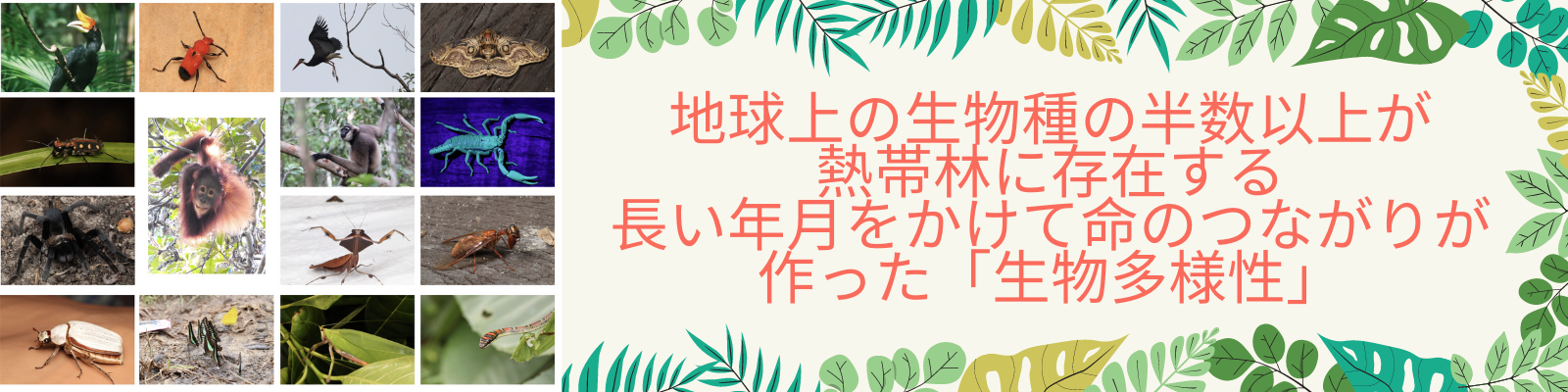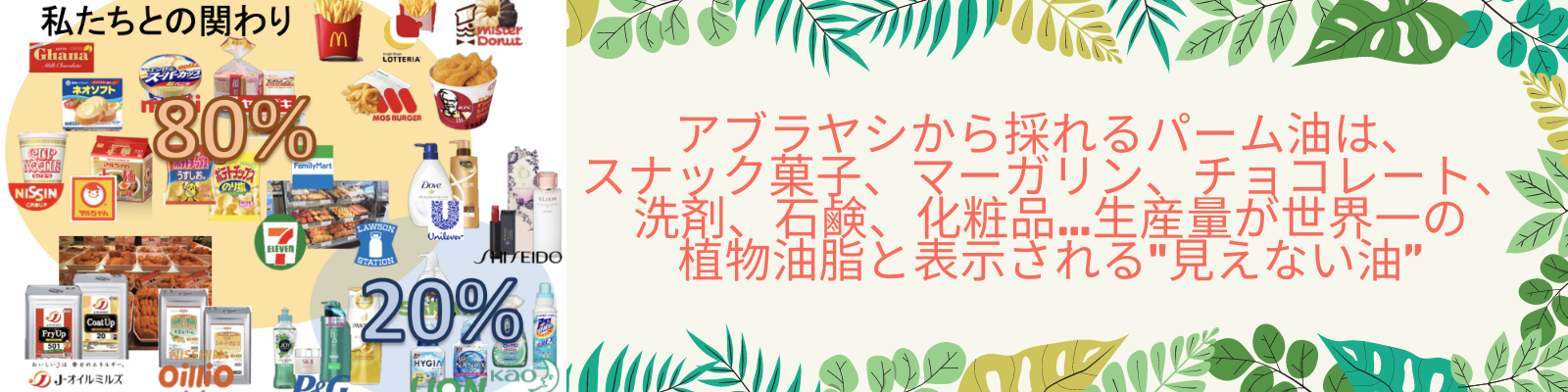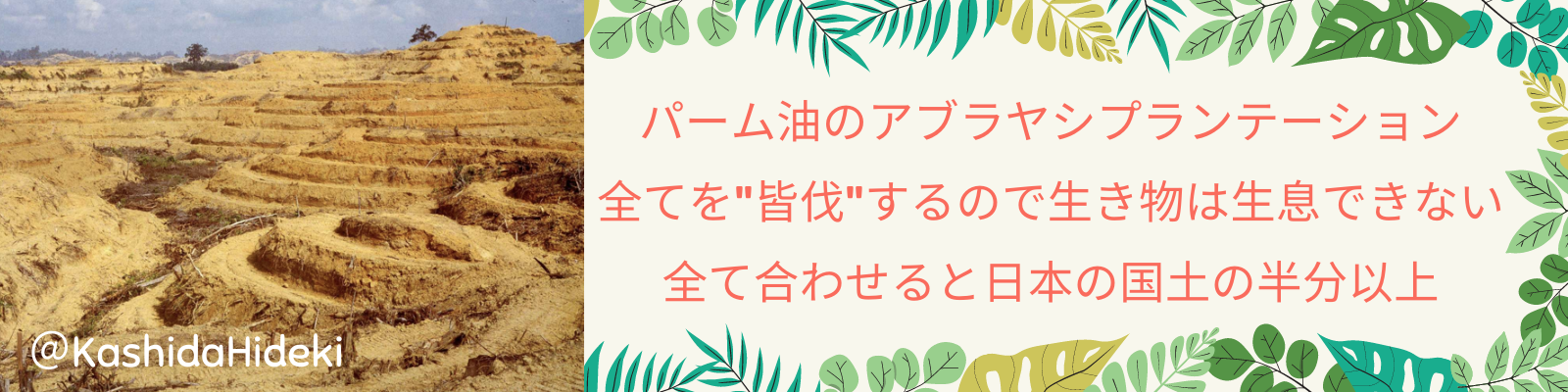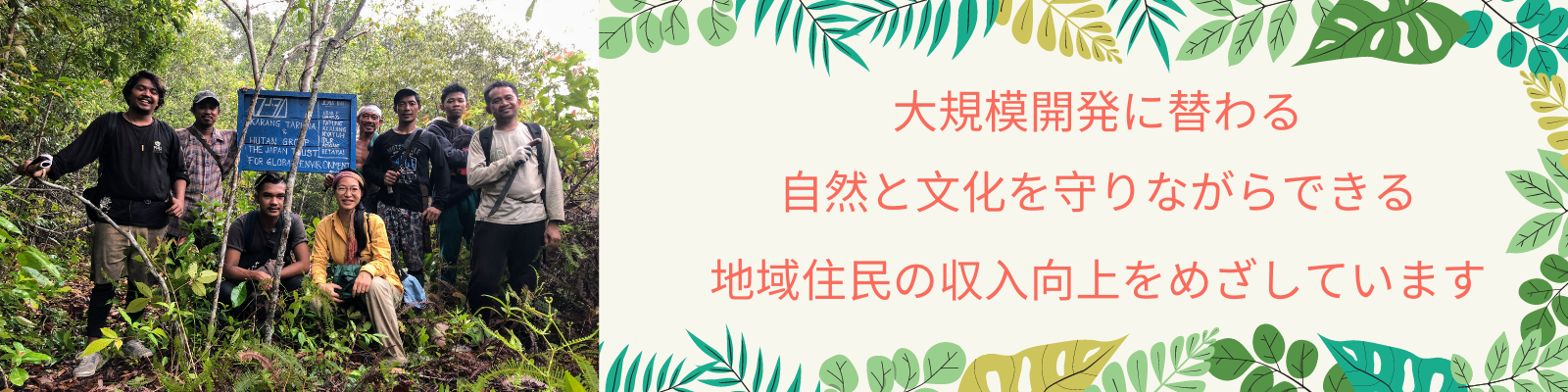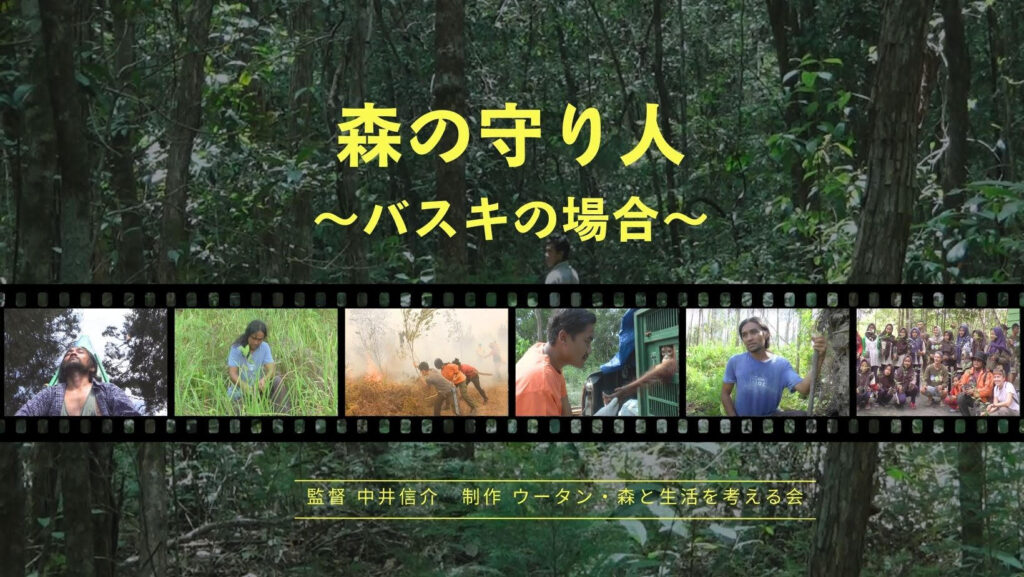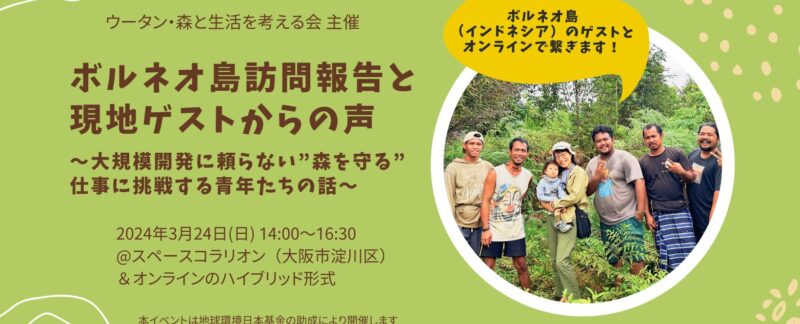6/22(日)13:30~17:30
ゲスト講演「生物多様性条約をめぐる先住民の交渉術」
&ウータン定期総会を開催します!
【講演会タイトル】
生物多様性条約をめぐる先住民の交渉術
~アマゾンでのCOP30に向けて市民セクターとして何ができる
今年の11月に気候変動枠組条約COP30が、ブラジルの都市ベ
世界最大の熱帯林が広がるアマゾンでの開催ということで、森林保
一方で、自然破壊を伴う再エネなどグリーンウォッシュ的な企業や
生物多様性が最も保たれる場所は、地域に根付いた先住民が暮らす
南米の先住民が集うであろうCOP30で、どのような声があがる
日 時:2025年6月22日(日)
(スケジュール)
13:30~15:30 ウータン総会
15:30~16:00 休憩
16:00~17:30 ゲスト講演会
*片方のみ・両方ともの参加どちらも可能です。会員でない方は総
*終了後に会場で大阪の有機野菜を使った料理の懇親会を予定して
場 所:スペースコラリオン(大阪市淀川区十三元今里2-5-17)
参加費:無料(寄付歓迎)
定 員:会場30人、オンライン100人(申込先着順)
申込み:専用フォームから
→https://forms.gle/hi3XuAiEPbb
※過去のイベントでお申し込み時にメールアドレスのエラーにより参加用zoomリンクをお届けできない方が一部いらっしゃいます。フォームに記入の際にはメールアドレスに誤りがないかご確認いただくようお願いいたします。
フォームへの入力が難しい方は、contact-hutan@h
(1)お名前
(2)連絡先
(3)報告会か総会のどれに参加か
(4)会場参加かオンラインか
(5)懇親会の参加の有無
をご記入のうえ、メールをお送りください。
お申し込みいただいた方に、開催日2日前を目処に会場の道案内や
【ゲストプロフィール】
三石朱美さん
一般社団法人JELF(日本環境法律家連盟)事務局
名古屋在住。全国各地の環境問題に取り組む弁護士のネットワーク
2010年の生物多様性条約COP10以降、生物多様性条約CO